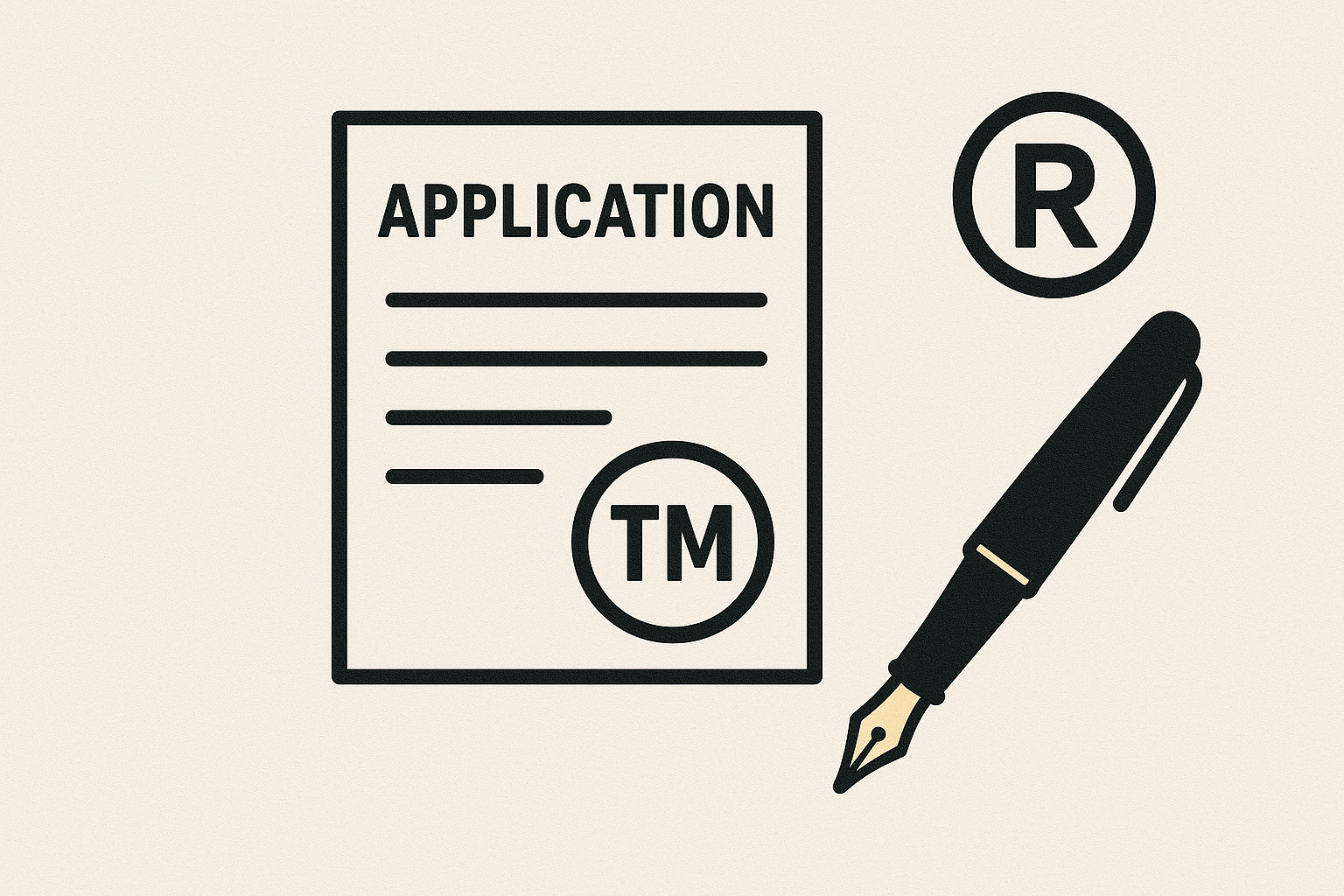記事公開日
最終更新日
商標登録にかかる期間と費用は?中間手続きについても解説

競争の激しい製造業において、優れた技術や製品を開発するだけでは、真の成功は掴めません。
他社に先駆け、自社のブランドを確立し、市場での優位性を確保するためには、戦略的な商標登録が不可欠です。
しかし、商標登録はただ申請すれば良いというものではありません。
迅速かつ効率的に進めるためには、登録にかかる期間や費用、そして重要な「中間手続き」といったポイントをしっかりと押さえておく必要があります。
そこで本記事では、製造業の企画部の皆様に向けて、これらの重要事項をわかりやすく解説し、攻めの知財戦略を実現するための道筋を示します。
<目次>
商標登録にかかる期間
商標登録は、出願してすぐに完了するものではなく、特許庁での審査を含めると約7カ月から1年以上の時間がかかるのが一般的です。
商標が正式に登録されるまでの期間を考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
本章では、商標登録にかかる期間の各ステップと、その目安について解説します。
商標登録の全体的な流れと所要時間
商標登録の流れは、大きく以下の5つのステップに分かれます。
| ステップ | 所要期間(目安) | 主な作業内容 |
|---|---|---|
| 事前調査 | 1日~1週間 | 既存の登録商標を検索し、登録可能性を確認 |
| 出願準備と書類作成 | 1~2週間 | 商標登録願、商標図案、指定商品・役務と区分の決定 |
| 特許庁への出願と形式審査 | 1カ月以内 | 書類の記載内容が正しいかチェックされる |
| 実体審査 | 6カ月~1年 | 商標が既存の登録商標と類似していないか等が審査される |
| 登録料の納付・商標登録 | 1~2カ月 | 登録査定後に登録料を支払い、商標登録証を受領 |
このように、商標を作成してから商標登録完了までには8ヵ月から1年以上かかるケースが多く、拒絶理由通知があればさらに手続きが長引くこともあります。
各ステップの詳細と所要期間
事前調査(1日から1週間)
商標を出願する前に、すでに類似の商標が登録されていないか、調査を行います。
■調査方法
- J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)や民間のDBサービスを利用して商標検索
- 弁理士に相談して詳細な調査を実施
事前調査が不十分だと、拒絶されるリスクが高まるため、しっかりと確認することが重要です。
「TM-RoBo」などのAIツールを活用することで、事前調査を効率的かつ効果的に行うことができます。
出願準備と書類作成(1週間から2週間)
商標登録願や必要書類を準備し、特許庁への申請に備えます。
■準備する書類
- 商標登録願
- 商標のデザイン(文字・ロゴなど)
■ポイント
- ミスがあると出願後に修正が必要になり、審査期間が長引くことがある。
- 指定商品・役務は、権利の範囲を設定しますので、狭く書きすぎると権利範囲が小さくなってしまいます。逆に、広く書きすぎると、既存の登録商標が原因で拒絶されやすくなります。指定商品・役務の設定は慎重に行うことが重要です。
- 設定した指定商品・役務に従って、区分を指定します。
関連記事はこちら
≫ 商標出願から商標登録までに必要な提出書類と作成上のポイントについて
特許庁への出願と形式審査(1カ月以内)
特許庁に商標出願を行うと、まず形式審査が行われます。
■形式審査でチェックされる内容
- 出願書類の記載ミスや不備がないか
- 指定商品・役務の区分選択が適切か
- 商標デザインの提出形式が正しいか
■特許庁から補正指示が出た場合
不備を修正して再提出(補正が必要な場合、さらに1~2カ月かかる可能性あり)
実体審査(6カ月~1年)
形式審査を通過すると、商標が登録可能かどうかを判断する実体審査に進みます。
■審査のポイント
- すでに登録されている商標と同一または類似していないか
- 識別力があるか
- 文字結合商標の場合、一部分に同一または類似する登録商標が存在する場合、その一部分が要部に該当するか否か
- 商品・役務の分類が適切か
- 公序良俗に反する表現が含まれていないか
■審査で拒絶されるケース
- 既存の登録商標と類似性が高い
- 識別力がない(一般名称やありふれた言葉、極めて簡単なデザイン等)
■拒絶理由通知が出た場合
- 意見書や補正書を提出(さらに2~3カ月かかる)
- 拒絶理由が解消されれば審査に合格となる(ただし、新たな拒絶理由が出される可能性あり)
登録料の納付と商標登録(1~2カ月)
審査に合格すると、特許庁から「登録査定」が通知され、登録料を支払うことで正式に商標登録となります。
商標登録に必要な費用
商標登録には、特許庁への出願費用や弁理士費用など、さまざまなコストが発生します。
総額でどのくらいの費用がかかるのかを事前に把握し、予算計画を立てることも大切です。
本章では、商標登録に必要な費用の詳細と、コストを抑える方法について解説します。
商標登録にかかる主要な費用一覧
商標登録にかかる費用は、以下の3つの段階で発生します。
| 項目 | 費用 | 説明 |
|---|---|---|
| 出願時の費用 | 3,400円 +(区分数×8,600円) |
商標登録の申請時に特許庁へ支払う費用 紙で行う場合は、別途電子化手数料として、2,400円+提出書類の枚数×800円が必要 |
| 登録時の費用 | 区分数×1万7,200円(5年間) 区分数×3万2,900円(10年間) |
商標が審査に通過し、正式登録する際に必要な費用 |
| 更新時の費用(登録10年以後) | 区分数×2万2,800円(5年間) 区分数×4万3,600円(10年間) |
商標権を維持するための更新費用 |
■注意点
- 商標登録は「区分」ごとに費用が発生するので(例:第9類(電気機器)、第25類(衣類)など)、費用の面からも必要な区分におさえるべき。
- 同一区分であれば、指定商品・役務をいくつ記載しても費用は変わらない。
上記は、2025年7月時点での料金です。出願時に必要な費用は随時改定される可能性があります。
■5年と10年、どちらを選ぶべきか?
長期間商標を使用する場合は、10年分を支払ったほうが割安です。事業の状況によっては、5年分だけ支払い、様子を見るのも一つの方法でしょう。
5年分を支払った場合、5年経過前に同額を支払うことで、更に5年の権利を確保できます。
■支払いのタイミング
登録査定通知が届いた日の翌日から30日以内に支払う必要があります。
更新時の費用(10年以後の支払い)
商標権を維持するためには、更新費用を支払う必要があります。
| 対象期間 | 費用(1区分あたり) |
|---|---|
| 5年分 | 2万2,800円 |
| 10年分 | 4万3,600円 |
■ポイント
- 商標権を継続するために、期限内に更新手続きを行うことが必須。
- 更新期限が過ぎると、商標権を失う可能性があるため、管理ツールを活用してリマインダー設定をすると安心。
- 登録時と同様に、5年づつ分納することが可能です。ただし、10年分まとめて支払う方が割安になります。
上記は、2025年7月時点での料金です。更新時に必要な費用は随時改定される可能性があります。
弁理士費用(依頼する場合)
商標出願を弁理士に依頼すると、専門的なサポートを受けられますが、追加で費用がかかります。
| 項目 | 相場(1区分あたり) |
|---|---|
| 商標出願サポート | 2~10万円 |
| 拒絶理由通知への対応 | 3~10万円(1回あたり) |
| 登録手続き代行 | 1~4万円 |
中間手続きとは?
商標登録の手続きには、出願から登録完了までの間に「中間手続き」と呼ばれるプロセスが発生する場合があります。
特許庁の審査官が出願内容を審査した際に、拒絶理由があると一応判断した場合や記載に問題があると考えた場合に、反論等を行う機会を与えるために拒絶理由通知等が発送されることがあります。
これに対して、適切な反論や補正等を行うことにより、拒絶理由等を解消し、登録に導くことが可能です。このような手続きが、中間手続きと呼ばれています。
適切に対応しないと商標登録が遅れたり、最悪の場合は拒絶されたりすることもあるため、スムーズな対応が求められます。
本章では、中間手続きの種類と対応方法について解説します。
中間手続きが発生するケース
商標出願後、特許庁の審査官による実体審査が行われ、拒絶理由通知等が発送されることがあります。主な拒絶理由等とそれに対する対応をまとめたのが下記となります。
| 原因 | 対応 |
|---|---|
| 出願内容に記載ミスがある | 手続補正書の提出 |
| 類似商標が存在し、登録が難しい | 意見書の提出 |
| 商標の識別力が弱い | 意見書の提出 |
| 指定商品・役務の分類に誤りがある | 手続補正書の提出 |
| 出願手続きが不適切(例:出願人情報のミス) | 手続補正書の提出 |
■ポイント
- 中間手続きは「特許庁からの通知」に基づいて行うため、通知が届いたらすぐに対応を検討する必要がある。
- 対応期限(通常40日以内)を過ぎると、商標登録ができなくなる可能性があるため注意。
主要な中間手続きの種類
手続補正書の提出
手続補正書とは、商標出願の内容を修正・変更するための書類です。
自発的に行うこともできますが、特許庁から手続補正指令書が出た場合、適切に修正を行い、期限内に提出する必要があります。
| 補正の対象 | 例 |
|---|---|
| 商標の表記の修正 | 誤字・脱字の修正 |
| 指定商品・役務や区分の修正 | 不適切な指定商品・役務や区分の記載を適切なものに変更 |
| 出願人情報の訂正 | 住所や会社名の修正 |
■補正のポイント
- 商標の内容そのものは基本的に変更不可(ただし、軽微な修正は可能)。
- 指定商品・役務の追加は不可(削除は可能)。
意見書の提出
意見書とは、特許庁の審査官からの拒絶理由に対して反論するための書類です。
審査官が「この商標は登録できない可能性がある」と判断した場合に通知される「拒絶理由通知」に対して、登録の正当性を説明するために提出します。
手続補正書を提出した場合も、補正内容とその正当性を説明するために意見書を一緒に提出することが望ましいです。
■拒絶理由の主なパターン
| 拒絶理由 | 対応策 |
|---|---|
| 類似商標がすでに存在する | 指摘されている登録商標と自社の出願商標が似ていないことを説明 |
| 識別力が弱い | 過去の判例や審決等を示し、登録事例があることを説明 使用により識別力を獲得したことを説明 |
| 指定商品・役務の記載が適切でない | 適正な指定商品・役務を指定し直す 指定商品・役務の記載が適切であることを説明 |
■意見書のポイント
- 法的根拠や過去の判例や審決を引用すると効果的。
- 弁理士に相談すると、より説得力のある主張が可能。
中間手続きの期限と対応方法
特許庁からの「補正指示」「拒絶理由通知」を受け取った場合は、発送日から通常40日以内に対応しなければなりません。
| 手続きの種類 | 対応期限 |
|---|---|
| 意見書の提出 | 発送日から通常40日以内 |
| 手続補正書の提出 | 発送日から通常40日以内 |
■期限を過ぎると…
- 商標出願が拒絶される(=登録不可)。
- 一度拒絶されると、最初から出願をやり直す必要がある(追加の費用が発生)。
- 期限が過ぎても、一定期間内であれば延長申請することも可能
まとめ
商標登録は、企業のブランド戦略において重要な役割を果たします。
期間、費用、そして中間手続きを理解し、戦略的に進めることで、市場での競争優位性を確立できるでしょう。
商標出願から登録まで、一定の期間と費用が必要となりますが、特許庁から拒絶理由通知が来てしまうと、登録までの期間は長期化し、費用も跳ね上がりますので、拒絶理由通知が来ないように十分な調査をしてから出願を行うことが強く推奨されます。
「TM-RoBo」などのAIツールを活用すれば、十分な商標調査を行い拒絶理由通知が来ないように準備することができますので、早く安く商標登録することが可能になります。
適切な商標戦略を構築し、ブランドを守るための対策を万全に整えましょう。
<関連記事>
商標の基本をまとめて確認!
商標の基本シリーズはこちらをクリック!
商標の最先端を現役知財弁護士が分かりやすく解説!
商標調査最先端コラムシリーズはこちらをクリック!
IP-RoBo広報部
執筆日:7月24日