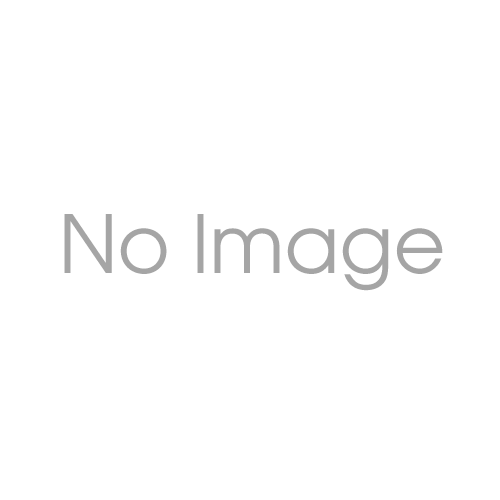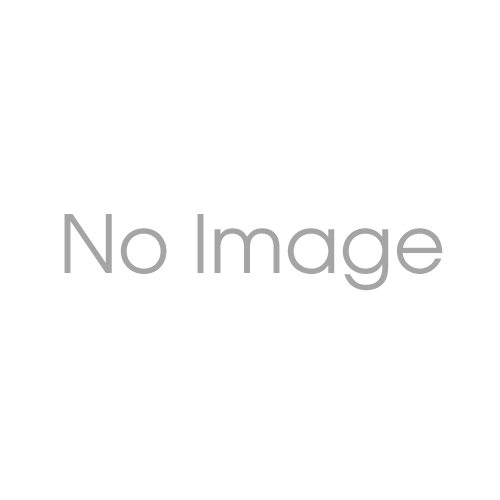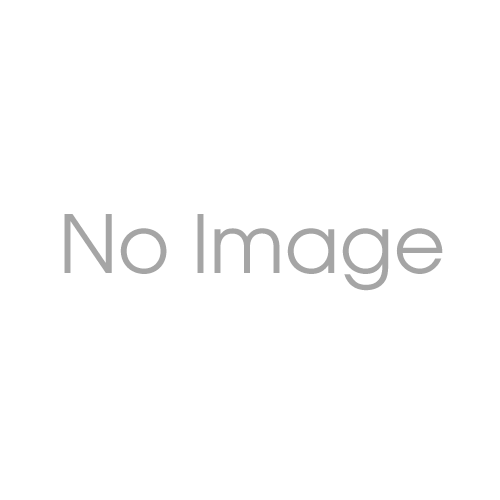記事公開日
最終更新日
【商標調査最前線コラムシリーズ第6回】AIは商標調査、商標検索の救世主となるか? ~長年の課題解決に向けたテクノロジーへの期待~

みなさん、こんにちは! IP-RoBoの岩原です。
私の執筆論文(※1)に基づいて商標調査の深淵に潜む様々な課題を探求してきたこのコラムシリーズ。第1回から第5回にかけて、商標調査を取り巻く根源的な問題点を明らかにしてきました。熟練した専門家の高度な判断やノウハウ、膨大な手作業が必要とされる現状は、調査の時間、コスト、そして見落としのリスクを高め、企業活動における製品開発やサービス提供のスピードを鈍化させる要因ともなっています。
今回は、こうした長年の課題に対し、最新のテクノロジー、特に「AI(人工知能)」がどのように貢献しうるのか、商標調査におけるAI活用への期待について掘り下げていきたいと思います。
(※1)技術情報協会「“知財DX”の導入と推進ポイント」401頁(2025年4月30日発刊)(https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2292.htm)
前回配信した「商標調査、商標検索、さらなる難関! ~「長い名前」をどう調べる? プロも悩む文字結合商標の壁~」もぜひご一読ください。
商標調査最前線コラムシリーズに関する解説動画が、知財オンラインにて公開されています。ぜひ下記リンクからご視聴ください。
解説動画:https://www.youtube.com/watch?v=wxi1ioaQDP0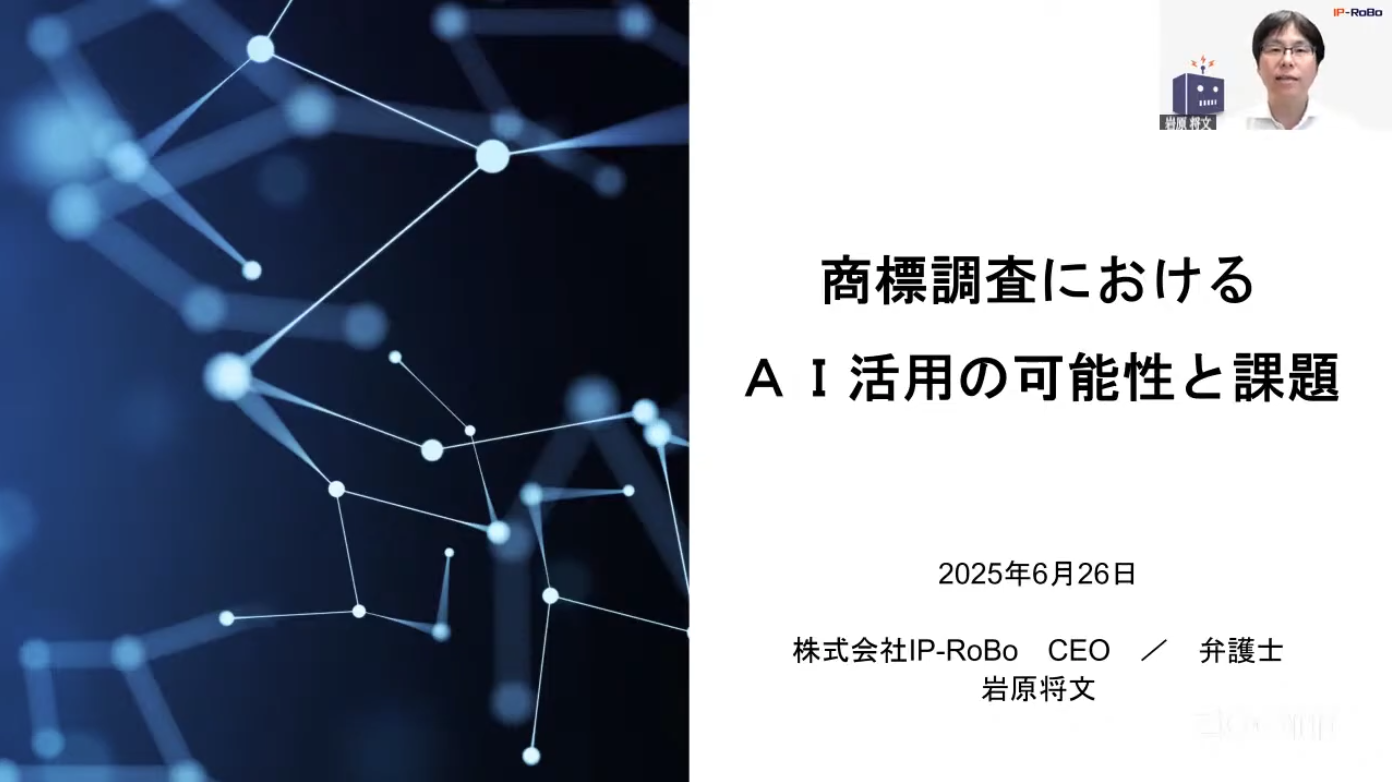
<目次>
法分野・知財分野におけるAI活用の波
近年、AI技術の発展は目覚ましいものがあります。特に、ディープラーニングに代表される機械学習が実用化された「第3次AIブーム」、そしてChatGPTに代表されるLLM(大規模言語モデル)が実用化された「第4次AIブーム」の盛り上がりに伴い、様々な分野でのAI活用が急速に進んでいます。
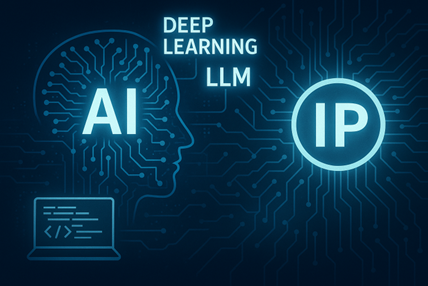
私たちの生活やビジネスのあらゆる側面にAIが浸透しつつある中、法分野や知的財産分野においても、AI化への模索が進められています。例えば、契約書レビューのような業務では、すでにAIによる支援ツールが実用化されつつあります。
知的財産分野においても、AIによる知財調査や出願書類作成といった業務の実現が期待されており、特許庁や民間サービス会社などで研究開発が進められています(※2、※3)。これは、複雑で専門性の高い知的財産業務において、AIがその効率化や質の向上に貢献できる可能性が認識されていることを示しています。
(※2) 特許庁「人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン(令和4~8年度版)」2022年
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-fy2022.html
(※3) 特許庁「アクション・プラン(令和6年度改定版)」2024年
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-fy2024.html
商標調査、商標検索におけるAI活用の可能性と期待
では、私たちがこれまで焦点を当ててきた「商標調査」の分野において、AIはどのような形で貢献できるのでしょうか。
商標調査の分野においてもAI活用の可能性が十分にあり、特に「商標の類否判断をサポートするAI」の開発が理論的には可能であると考えられています。その根拠として挙げられているのが、「特許庁や裁判所における類否判断が長年にわたって蓄積していること」です。これらの公的な判断事例は、商標の類否判断における重要な基準や傾向を示しており、この膨大なデータをAIに機械学習させることで、ある程度客観的かつ精度の高い類否判断をAIが行えるようになる、という期待です。
そして、そのような商標の類否判断をサポートするAIが実用化されれば、前回までに述べた商標調査、商標検索の現状における課題は大きく改善され、商標調査、商標検索が劇的に効率化されると考えられています。
商標調査、商標検索の課題に関する記事はこちらから
≫ 商標調査、商標検索、なぜそんなに大変なの? ~「似ているか」を見分けるプロの悩み~
≫ 商標調査、商標検索、さらなる難関! ~「長い名前」をどう調べる? プロも悩む文字結合商標の壁~
≫ 商標調査、商標検索の隠れた壁 ~見た目の判断もAI任せにできない!? 図形商標の調査、検索の深淵~
AIはどのように商標調査、商標検索の課題を解決しうるか?
これまでのコラムで述べてきた具体的な課題と照らし合わせながら、AIによる「類否判断サポート」がどのような効果をもたらしうるのか、さらに詳しく見ていきましょう。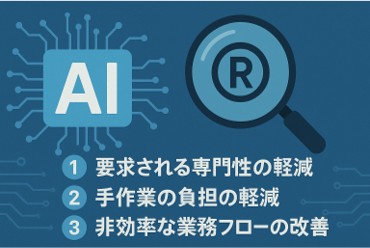
(1) 類否判断の専門性・属人性の軽減
文字の称呼判断、結合商標の要部認定、図形商標の類否判断といった、専門家による高度な知識と経験に依存していた判断作業において、AIが特許庁や裁判所の判断傾向を学習した結果を提示することで、専門家の判断をサポートし、判断のブレを減らすことが期待できます。これは、調査結果の信頼性を高め、見落としリスクを低減する可能性を秘めています。
結合商標に関するコラムはこちら
≫ 商標調査、商標検索、さらなる難関! ~「長い名前」をどう調べる? プロも悩む文字結合商標の壁~
(2) 検索・分類の効率化、手作業負担減
図形商標の複雑な分類や、称呼・外観・観念といった複数の観点からの検索は、既存のデータベースではそもそも対応していないことも多く、対応している場合でも非常に手間がかかりました。AIが商標の画像や文字情報から自動的に特徴を抽出し、類似度の高いものを効率的に検索・提示できるようになれば、専門家が膨大な検索結果を目視で一つ一つ確認する手作業の負担を大幅に軽減できるでしょう。
図形商標に関するコラムはこちら
≫ 商標調査、商標検索の隠れた壁 ~見た目の判断もAI任せにできない!? 図形商標の調査、検索の深淵~
(3) 業務フロー改善(二段階調査支援)
第5回で述べたように、商品開発部など非専門部署による一次調査(ファーストスクリーニング)の実現は、現在の業務フローの非効率を解消する鍵となりますが、既存ツールの専門性の高さがその壁となっていました。もし、AIによる類否判断サポート機能を備えた、より直感的で使いやすいツールが登場すれば、専門知識がない担当者でも一定の精度で簡易的な一次調査を行うことが可能になるかもしれません。これにより、知的財産部への調査依頼が絞り込まれ、二段階調査という理想的なワークフローの実現に大きく近づく可能性があります。これらの点においてAIが貢献することで、商標調査にかかる時間とコストが大幅に削減され、より迅速な製品開発やサービス提供が可能になることが期待されます。また、調査漏れによる無用な争いや損害のリスクも低減されるかもしれません。
二段階調査に関する記事
現場の一次スクリーニングと知財部の最終判断による“二段階調査”を実現
≫ 事業部との連携による二段階調査
商品開発部にAI商標調査ツールを導入し、調査効率を向上させた企業の事例
≫ 現場と知財部門の垣根を超えた、理想の知財経営
まとめ AIは救世主となりうるか、そしてその先へ
商標調査におけるAI活用、特に類否判断サポートAIの実用化は、これまで見てきた商標調査の難しさ、属人的な専門性、手作業への依存、そしてそれに起因する業務フローの非効率といった、長年の課題を解決するための非常に強力な武器となりうる可能性を秘めています。特許庁や民間サービス会社も研究開発を進めていることからも、その期待の高さがうかがえます。
しかし、AIによる類否判断はあくまで「サポート」であり、最終的な登録可能性の判断やリスク評価は、引き続き商標法の専門家である弁理士や弁護士、知的財産部などの担当者によって行われる必要があります。AIの判断の精度、判断根拠の透明性、そして法改正や社会情勢の変化への対応など、実用化に向けてはまだ様々な技術的・法的な課題が存在することも忘れてはなりません。
AIは、専門家の役割を完全に置き換えるというよりも、彼らの負担を軽減し、より高度な判断や戦略的な業務に集中できるよう支援する、強力な「協働パートナー」として、商標調査の未来を切り開いていく鍵となるでしょう。
次回は、商標調査AI実現における技術的な課題、特に文字商標調査AI実現における技術的な課題について、さらに深く掘り下げて検討していきたいと思います。
≪関連記事はこちら≫
次回(第7回):8月上旬公開予定
前回(第5回):商標調査、商標検索の隠れた壁 ~調査プロセスそのものに潜む非効率と、理想のワークフロー実現を阻む壁~
******************************************************************
[ 執筆者 プロフィール ]
岩原 将文 /株式会社IP-RoBo CEO 弁護士
主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。
大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。
<関連リンク>
WEB:https://ip-robo.co.jp/
お問い合わせ:info@ip-robo.co.jp またはお問い合わせフォームから
******************************************************************